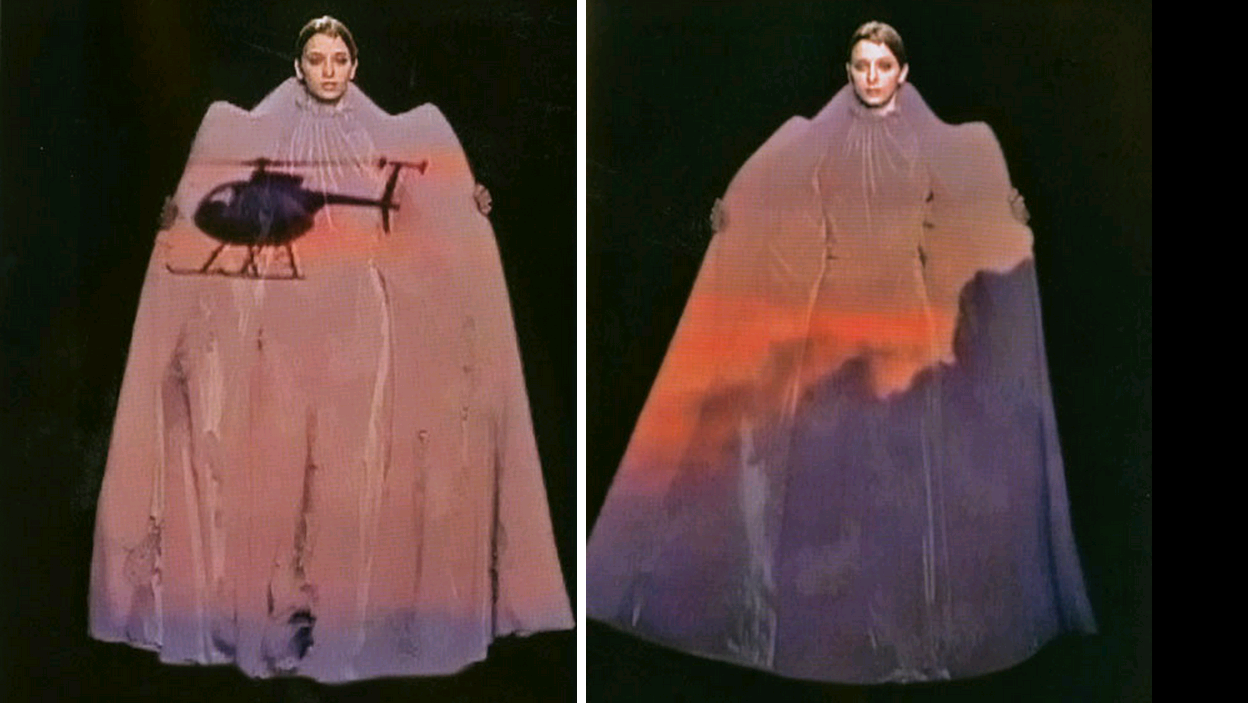演劇は、試算にたいして軽やかでいいなと思う。なにかを確かめようとする逡巡が、そのまま身体に、言葉に、空気に乗っていって、不安定なまま伝播する。俳優の手の震えや、不自然なまばたき。コントロールされきっていない生ものの気配。
関田育子『浜梨』において、65分間だけこの世に現れる肉体たちは、この世界にたいして無責任だ。彼らの身体はこの世のルールになんて即していなくって、それに規則性を見出すのも、意味を見出すのも、理解を試みるのも、舞台をじっと見つめる私たちである。『浜梨』は難解ではない。ほぼすべての台詞が明快に意味を持っている。少しおかしなのは人間同士の位置関係で、現実の物理的規則とは少し離れたところに、彼らの身体はあるように見える。言うならば漫画のコマ。あるいはテレビドラマのカメラワーク。
たとえば。ねえ、お父さんの寝癖直してちょうだいよ、そのヘアアイロンで、と頼まれていやいやそのお願いを聞く娘。父と娘(で、あるところの、20代くらいの、男女)は客席に正対して立つ。娘は客席に向けて、ヘアアイロンを扱う仕草。その力の延長線上に父はいないけれども、父は髪の毛を引っ張られる演技。ヘアアイロンなどないし、加わる力などないし、そもそも寝癖なんてないというのに、私たちの頭の中で一連の力が現前する。
あるいは。上り棒登れる?えっちゃん、と1年生に聞く上級生。えっちゃん(と、呼ばれた20代くらいの、女)は、上り棒を登っていく仕草をしたあとに、斜め下を見下ろして手を振る。上級生(で、あるところの、20代くらいの男)はそれを見上げる。もちろん、舞台に上り棒などない。ふたりの立つ地表面に変化はないため、ふたりはずっと同じ高さにいるが、お互いに見下ろし見上げられている。このとき、斜めを向くふたつの視線は平行線を描く。
交わらないけど〈 交わっていることになっている 〉力や視線のベクトル。漫画の1コマ目に、ある方向を向く主人公の目、その次のコマに駅の時計が描かれているとき、〈 主人公は時計を見たことになる 〉。限られた紙面に駅構内全体を描くわけにはいかないから、視線のはじまりとおわりだけを描く。あとは読者が勝手につなげてくれる。『浜梨』を構成していたのは、このぶつ切りの力だ。空間の広さも、作れるセットも、移動に関する人間の身体能力も限られているとき、その有限のなかで動きを見出す技法。パントマイムは力の軌跡を描いて無いものを現前させるけど、この舞台は力すらも省略する。
- - -
力の最初と最後だけが描かれるとき、そこで起きるベクトルとは無関係に、力点と作用点が隣接する。これがコマなのであれば脳で起きる処理は単純だけれど、曲がりなりにも現実空間である以上、質量と影をもつ人間の身体が力にたいして不自然に連続している事実に、私たちは自動的に戸惑う。自動的に戸惑いながらも、頭で力の流れを理解し、なんとか納得しようとする。繋がれた( 繋がれていない )手、睨み合う( 睨み合わない )3人、抱擁する( 抱擁しない )2人。示されながらも噛み合うことのないいくつもの力に、次々と判断を迫られる。記号か、身体か。どちらを信じるべきか。どちらの形式の情報が、より正確に客席まで届くのか。
記号と身体。この拮抗するふたつの情報の狭間で揺らがされ続けるのが『浜梨』なのだけれど、これは同時に、複数の視線に同時に晒される身体が、その不確かさを保ちながら、なるべく平等に意味を配布するための技法でもある。6560×2800。会場であるSCOOLの部屋の断面。この面全体が、観客の視線を想定している。私の位置は右側前方下より、という偶然座った一点であり、他の人の位置はまたちがう。視線が想定される面が広いということは、それだけ俳優同士のコンポジションを決めるのが難しいということだ。だって顔なんて、ある席の角度からは見えないときだってあるし、キスシーンが嘘っこなのも、簡単にばれちゃう。
ところで、記号は。記号が差し示すものには嘘も誠もない。角度による曖昧さもない。泣き顔はときに笑い顔にも見えるけれども、涙を拭う動きは涙を拭う動きにしか見えない。その手の後ろで俳優がつめたい無表情な目をしていようとも、そこに現前するのは悲しみなのである。