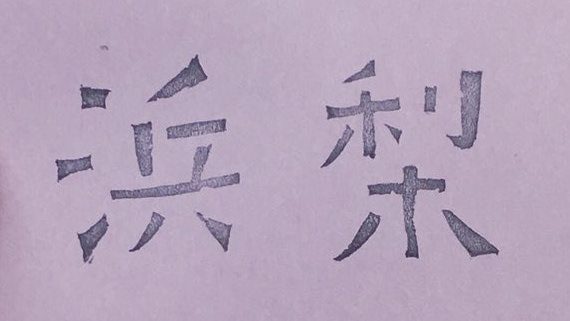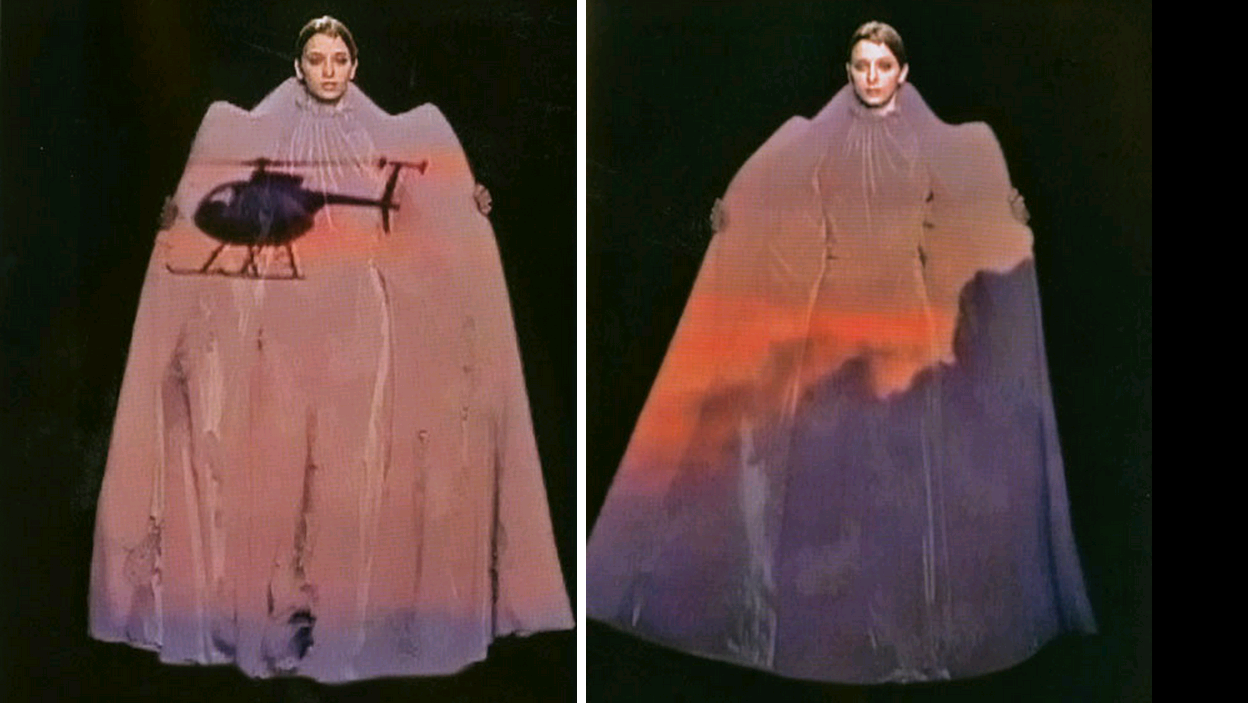2023年10月21日の日記。
ひさびさに実家に帰ってきて、カーテンを閉めた家の暗さに、目が見えなくなったのかと思った。京都で住み着いた町家はほとんど外部のようなもので、月の明るさや街灯と縁が切れることがない。
今日は風邪ぎみで息があまりできていないまま、よみうりランド前で降りて粟津邸(設計:原広司)へ。面白い時間を過ごした。息ができていないことも、急いで買い足したカメラのフィルムがセールで1本1690円だったことも、どちらも帳消しになった。下記は備忘録としての日記。いつかなにかしらを確かめて追記したりするかもしれない。いずれにせよ、あまり息ができないまま書いているので歯痒い。
まず。対称形の荘厳な軸線空間 (原広司自邸とも共通する、内包された都市、とも言われている部分。反射性住居の特徴たる部分。) の写真からの印象は、実を言うともう1.5倍くらい広い体感なのかと思っていた。壁は思ったよりも近く、思った以上に塗装された板であった。踏み入れた最初の印象は、空間を貫く軸線は充分に深いが、その両脇の列柱のようなドームのついた意匠は、もっと大きなスケールにふさわしい意匠ではないかというもの。むしろ全体の構成よりも、おそらく床付コンセントの蓋を避け1枚抜けたタイルや、板材の勝ち負けが残る塗られた小口など、親密な手つきのほうが目に入ってくる。
2層ひといきに奥まで降りて方向転換し、最奥部の水廻りや茶室をうろうろとまわると空間のスケールはどんどん小さく入り組んでいって、この住宅が深いだけでなく大きいことに気がついてくる。谷に落ちていった方向と逆を向いて階段を登っていくと、騙されているのかと思うほどに奥行きがある。上部の窪んだ天井の側面にトップライト。同行者が、このトップライトの上にあるのは室内じゃなくて屋外だ、外のアプローチの通路の横にあった開口だ、これを上階の内部空間のように錯覚するから余計に空間が広く感じる、と言い出し、少し話す。新しい訪問者が来るたびに一瞬陰る開口を階下の室内からじっと見上げる。
( 都市を内包する )、これは室内に外皮をもったヴォイドを作り、その裏表が翻りながら併存するということだけではなくて、その建築の本当の屋外さえも仮想のヴォイドのように内包する、ということなのかもしれないと思いはじめる。RC壁面の中に完結しない、そのさきに境界もなにもない本当の屋外を、屋内にせり出してきた窪み、という認識の延長上で内包している。


徐々に。スケールにそぐわないほど大きく近く見えたドーム付きの装飾は、その裏のわざとらしいほど深いトップライトのためにあり、快適な室内空間のために庭へと開く子供部屋の開口も、その裏の庭側に現れる姿のためのようにも見えてくる。木で設られた室内の壁や床、そして庭との区切りとなる壁面、どこまでも分け隔てなく、物体には表面があれば裏面がある、そこにある以上は素材感がある、吹き抜け空間に向けられたデスクの足元の開口も、上段がセットバックした収納扉さえも、等しく表側と裏側があり、その表面を舐めるように、形は作られたままに存在する。
物質性を吹き飛ばし空間を荘厳に見せるには、たとえば素材そのものを際限なく高価で大きなものにするか、目を疑うほど精緻な装飾で覆うか、あるいは空間自体のスケールをものすごく大きくして、人の目から平らに見えるようにし、抽象度を上げるか。そんなことをぼんやり夢想するが、 ( 住宅 ) という条件の上ではどれも現実的でない。多数の人間がさわり、そしてまた経年によりひび割れ、歪む、そんな建築の取り繕えなさを抱えた上で、実体と言葉を共存させて空間を作る可能性は本当にあったのかもしれないと、初めて思えたような気がする。